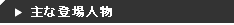



IPO最新情報や西堀編集長のIPOレポート、FXストラテジストによる連載コラム、コモディティウィークリーレポートなど、今話題の様々な金融商品をタイムリーにご紹介するほか、資産運用フェア、IRセミナーのご案内など情報満載でお届けしています!

|

|
|
|

『パラダイス』はポリネシアの家屋をイメージした内装になっていて、アジアやその他の南洋の島々の料理を売り物にしている。2人はまず『ピナコラーダ』で新年を祝って乾杯した。
アペタイザーに『サテー』(アジア風の串にさした焼き鳥)の盛り合わせを注文した。メインに菜緒子はインドネシアの料理『ナシゴレン』(インドネシア風炒飯)を、慎介はタイのココナツミルクの入ったグリーン・カレーを頼んだ。
「おせちに飽きたらカレーっていうコマーシャルがあったな」慎介がぼそっと呟いた。
「おせち食べたの」菜緒子はにやっと笑いながら訊いた。
「ここ何年か食べてないよ」
「あらそう。慎介も、お正月そうそう大変よね」菜緒子が同情するように言った。
「まあ、お役所のやる事だからね。毎度の事ながら市場の動向よりも彼らの都合が優先する訳さ」
「勝手なものね」
「まあな。でもこのディールはなんとしても射止めないと。リバティー・ワンの奴等には負けられないからな」
「大変ね。手におえない大人の喧嘩って」菜緒子は自分が桟敷席の見物人ぐらいのつもりなのだろう。
「まあな。でも悲しいかな現実なんだよね」
「私たちも1月半ばにはそちらに引っ越す事になっているみたい。よろしくね」
「こちらこそ。お手柔らかに頼むよ」
慎介はコロンビアのビジネス・スクールで一緒に勉強していた頃から、菜緒子のことを何処かで意識していた。食事中もおおらかに笑う菜緒子の柔らかそうな唇を見て、慎介は何処か心の隅にしまわれていた意識が深い眠りから目覚めるのを感じた。2人はいろいろな事を話した。慎介と菜緒子は同じ1964年生まれだが、菜緒子の方が早生まれで1学年上だった。
「今年は私達ぞろ目の33歳になるわね。このまま仕事だけで終わってしまうってのも考え物よね」菜緒子は感慨深げに言った。
「落ち着き先の当てでもあるの」慎介は尋ねた。
「そんなもんあったら、今ごろはハワイかどこかのビーチで二人で楽しんでるわよ」
「そういう慎介こそどうなのよ」勝ち気な菜緒子は反撃にでた。
「まあ、募集中ってとこだな」焦って慎介は返答に窮した。
「転勤になってニューヨークから戻ってきた頃は、親とか親戚とかその取り巻き達が、挙って見合い話を持ち込んできて、うんざりしていたんだけど、いざ、何も話しが来なくなると、またそれはそれで複雑な気持ちになるのよね」ピナコラーダの所為か菜緒子はいつもにまして饒舌になっていた。
「俺なんてどう」慎介が照れながら言う。
「えっ!」菜緒子は面食らった様子で、次の言葉が見つからない。
「ご、ごめん、心の準備が出来てなかったから。でも、慎介、悪い冗談でしょう?」
「ううん、けっこう俺は本気だよ」慎介は自分に言い聞かせるように言った。
2人を沈黙が襲った。お互いに次の言葉が出てこない。2人は互いに意識しあっている自分自身に気付いた。ウエィターが二人のテーブルまで来ると空いた皿を下げ、食後のデザートを奨めた。2人はメニューからデザートを選び、エスプレッソを一緒に注文した。夕食を終えると2人は歩いて道路を挟んで反対側にある『ホテル・ドゥ・赤坂』の最上階のバーに場所を移した。
ジャズ・ピアノが切ないメロディーを奏でていた。2人は東京の夜景が見渡せる窓際の2人掛けのテーブルに通された。中央のS字形にカーブしたカウンター・バーのスツールに浅く腰を下ろした人待ち風の外人客が葉巻をくゆらせている。『コヒーバ』の馥郁とした香りが鼻孔を心地よくついてくる。葉巻の紫煙が紗の薄く透き通ったベールのようにあたりの雰囲気を柔らかく包み込んでいた。黒服のウェイターが片手に持った磨き上げられた銀色のトレイからドライ・マティーニのグラスを2人の前にそっと置いた。乾杯して、2人は無言のままグラスの中身を啜った。慎介は一瞬時間が止まってしまったような錯覚に見舞われた。
「慎介」沈黙を破ったのは菜緒子だった。
「何?」慎介は我に帰ったように答えた。
「さっきの申し出の件だけど、暫く預からせてくれないかな?」
事も無げな雰囲気を装って慎介は気乗りしない様子で答えた。
「いいけど。暫くってどのくらい」
「さあねえ・・・…」余韻を残しながら菜緒子は小悪魔的な面持ちで外の夜景に目をやった。
その後2人はいつものように時の経つのを忘れて話し込んだ。コロンビア大学時代のことや仕事のこと、家族のこと、将来のこと、いろいろなことを。気が付くと時計はすでに午後11時を回っていた。
2人はタクシーに乗るとホテルを後にした。運転手に行き先を告げると、2人の間には再び静粛が訪れた。通りを行き交う車の数が少ない所為か、飛行機の客室のようにエンジンの音だけが聞こえてくる。街のネオンも普段の輝きを無くし、淋しい感じだけが誇張され漂っていた。車は幹線道路を外れ、住宅街に入った。人の気配が全く感じられない完全な静けさの中に車は吸い込まれていった。菜緒子のマンションの前で車は静かに停止した。菜緒子は慎介の顔を見て言った。
「慎介、ちょっと寄っていきなよ、コーヒーでも煎れるから」
慎介は頷くと菜緒子と一緒に車を降りた。菜緒子の後をついて大理石のエントランス・ホールに入った。2年前のクリスマス・イブの日に慎介はまさにこの場所で菜緒子に口付けをしたのだった。その時の事が鮮明に脳裏に蘇った。慎介の歩調が緩慢になり、先を歩く菜緒子との距離がひろがった。菜緒子が慎介の方に振り返った。
「どうしたの?」と心配そうな顔で訊いた。
慎介は菜緒子に心の内側を見られたような気がして、恥ずかしくなった。
「ううん、なんでも」と慎介はその場を取り繕った。
菜緒子の部屋は2階の奥の東南に面した角部屋にあった。菜緒子は玄関の脇のインターフォンの横にあるセコムの錠を解除して玄関の扉を開けた。部屋はステューディオ・タイプのつくりで、ベッド・ルームと広めのリビング・ダイニングから構成されていた。リビングにはぺバーミント・グリーンのソファが壁を背にして置かれていた。照明はすべて間接照明で、菜緒子のセンスが感じられた。菜緒子は慎介をソファに案内して、「その辺で、寛いでいて、すぐにコーヒー入れるから」そう言い残すと菜緒子は寝室に着替えに行った。
「有り難う、そうさせて貰うよ」慎介は悪いと思いながらも、部屋の中をきょろきょろと見回した。部屋の至る所に菜緒子らしさが溢れていた。慎介はリビングのサイド・ボードの上にあるシステム・コンポに目が止まった。ためらって慎介は言った。「なにかCDでも聞かない」
オレンジ色のシャツにジーンズ姿の菜緒子が出てきて言った。
「サイド・ボードの横にCDが何枚かあるから、それから何か適当なものをかけて」菜緒子はコーヒーの準備をしながら目でサイド・ボードの右側を示した。慎介は5枚程あったCDの中から、去年ヒットしたドラマのサントラ版を見つけた。慎介のお気に入りの男性シンガーがその主題歌を歌って、ミリオンセラーになった曲がはいっていた。慎介は迷う事なくそのCDをステレオにいれて再生ボタンを押した。その時、慎介はステレオの横にある木製の写真建てに気付いた。見覚えのある古い蔦の絡まる石造りの建物のまえで若い男女がふたり肩を組んで笑って正面を見ている写真だ。それはコロンビア大学の校舎のまえで慎介と菜緒子が2人で撮った写真だった。聞き覚えのある心地良い声とメロディーがスピーカーから流れた。菜緒子がコーヒーを運んできた。2人で並んでソファーに腰を掛け、コーヒーを飲んだ。CDが軽快なアップ・テンポからバラード調の曲に変わった。2人は言葉を交わすこともなく、だだ時間だけが悠々と大河の如く流れていた。慎介の左腕と菜緒子の右腕が触れた。慎介は菜緒子の目を覗きこんだ。大きな瞳に慎介自身が映し出されていた。慎介が右手をそっと菜緒子の左肩にかけると、菜緒子は軽く目を閉じた。慎介は菜緒子の柔らかい唇を人差し指の腹で繊細なものを触るかのように右から左にそっと這わせた。慎介は左手で菜緒子を包み込むように抱き寄せた。菜緒子の首筋からうなじにかけて、慎介は唇でなぞった。菜緒子の口から甘く切ない弱々しい声が洩れた。
「慎介、くすぐったいわ」菜緒子が囁く。
菜緒子の愛用の香水のセクシーな芳香が慎介の心を激しく揺さぶった。慎介は菜緒子の唇に自分の唇を重ねた。フロア・ライトが白い壁に映し出す2人の影が1つになった。慎介は自分の体に電気のような衝撃が貫くのを感じた。慎介は菜緒子のブラウスのボタンを優しくはずした。白い肌が露になる。慎介は菜緒子の下唇を軽く噛むと、首すじから胸元にかけて唇を這わせ、優しく愛撫した。菜緒子も慎介のジーンズのベルトにその細い指をかけた。やがて2人は一糸纏わぬ姿になり、お互いに見つめあい、深い官能の迷宮に落ちていったのだった。
|
|