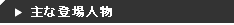



IPO最新情報や西堀編集長のIPOレポート、FXストラテジストによる連載コラム、コモディティウィークリーレポートなど、今話題の様々な金融商品をタイムリーにご紹介するほか、資産運用フェア、IRセミナーのご案内など情報満載でお届けしています!

|

|
|
|

大澤源太郎はお気に入りのキューバ産の葉巻『コヒーバ』を専用のシガー・カッターで上手にカットするとマッチで火を点けた。葉巻独特の香りが市田の鼻腔を撫でるように流れ込んだ。大澤は香りに酔いしれて、麻酔を打たれた後の様なけだるい感覚に身を委ねていた。市田と大澤は昼食を済ませてから、パシフィック・ホテルの1階の片隅にあるシガー・バーで内密の話をしていた。時計は午後1時半を回り、バーには2人以外の客は誰もいなかった。深く腰掛けてソファーに埋没せんばかりの体勢で大澤が言った。
「市田さん。顔色が優れませんね。どうかされましたか」
「いや、別に何でもありませんが」
大澤は蛇のような邪悪な目をして続けた。
「市田さん。私と貴方の間で隠し事は無しですよ」
「ええ、それはもう十分に承知しています」
「今日の貴方を見ていると、とてもそうは思えないのですが…、何か気になっている事があるのですね?」
「ええ、まあ…」市田は湯川亜実からもらった電話の件を大澤に打ち明けるべきがどうか思案していた。
「貴方が危惧する事は私にとっても危惧すべき事である可能性があるという事なんですよ。何事も手遅れにならないうちに手をうたないといけません」大澤が発する奇妙なプレッシャーに気圧されて市田は湯川亜実の件を大澤に告白した。
「ほら市田さん、こんなに重要な事があったんじゃありませんか」大澤は批判めいた口調になった。市田は湯川亜実が同業他社に転職していて、今は自分の手の届かない所にいる事実を大澤に伝えた。
「前回のようなわけにはいかないわけですね」葉巻をくわえた大澤の唇の間から覗く白い歯が光った。市田はあの仕組まれた飯野菜緒子のひき逃げ事故の件が頭を過ぎり突然悪寒が背筋を走るのを感じた。
「もう、あそこまでする事はないでしょう」市田が恐る恐る言った。
「それに湯川は私たちの事は何も知らない訳ですから」
「まあ、それも一理ありますね。湯川亜実さんか、活発なお嬢さんでしたよね」
市田は大澤が何を考えているのか想像しただけで、その場から一刻も早く立ち去りたかった。
「彼女の件は私に任せて下さい」大澤がニヤリと笑った。
「まさか…」市田の顔が不安で曇った。
「市田さん、ここは日本ですよ。私もそんな無茶はしませんよ。ご心配なく。取り敢えず、彼女の勤め先と住所を後で知らせて下さい」
その日、湯川亜実は顧客へのプレゼンテーションの準備の為に遅くまで仕事をしていた。準備が一通り終わったのは時計の日付が変わってから随分たった頃であった。同僚と日比谷通りに店を出している屋台でラーメンを啜ってからタクシーに乗った。亜実のタクシーは日比谷通りを芝公園の方に走りはじめた。その時、やや距離を置いて、一台のわナンバーを付けた黒のシルビアが亜実の乗ったタクシーの後をなぞる様に走っていた。タクシーは御成門の交差点を右折すると神谷町の方面に抜け、桜田通りを左折し、飯倉の交差点を右折してロシア大使館の先を左にそれて坂を下って行った。坂を下りきった突き当たりのT字路の右側に小さな公園があった。その公園の脇にあるマンションの3階に亜実は住んでいた。時計は午前2時を回り、通りには人っ子1人いなかった。亜実を乗せたタクシーはT字路を右折して公園の角で止まった。シルビアに乗っていた男はタクシーから見えない様にT字路の手前で車を止めると助手席に放ってあった黒い毛糸の覆面と黒の革の手袋を手に取り公園の中に入って行った。亜実は支払を終えて歩道に降り立った。公園の前の歩道を通ってマンションほうに歩いて行こうとした。その時、公園の暗闇から黒い影が飛び出してきて亜実の前に立ちはだかった。亜実はあまりの突然の出来事に身動きが出来ず、金縛りにあったようにその場に立ち尽くしてしまった。男は亜実の口元を片手で抑えるとそのまま後ろから羽交い締めにして亜実を公園の暗がりに連れ込んだ。亜実はあまりの恐怖に声すら出なかった。何とか助けを求めようともがいてみたが、亜実の首筋に入り込んだ男の腕はびくともしなかった。男はじわじわと亜実の喉元を締め上げていった。次の瞬間、男はお尻のポケットからバタフライ・ナイフを取り出し、その刃先で亜実の頬を撫ではじめた。男は亜実の喉を締め上げていた腕の力を少し緩めた。亜実はかろうじて出来た気道の隙間から貪るように空気を吸うと、そのあと激しく咳き込んだ。男は亜実の耳元で囁くように言った。
「そのかわいい顔に傷をつけたくなかったらマニラの事故の事は忘れろ。忠告を無視したら後は無いと思え。分かったか」男は激しく亜実の頭をゆさぶった。
「分かったか」男は繰り返した。亜実は恐怖のあまりなんとか頷くだけだった。男は満足したらしく、亜実を地面に叩きつけるように背中から力一杯突き飛ばした。亜実はもんどり打って前につんのめった。頭を地面に強く打ち付けたらしく、亜実は朦朧とした意識の中で男の足音が遠ざかって行くのを聞いた。それからどれくらいの時間が経ったのだろう亜実は自転車に乗って警邏中の警察官に公園で倒れているところを発見されたのだった。
窓越しに指し込んでくる朝の光が亜実を深い眠りの淵から呼び起こした。うっすらと目を開けると真っ白な天井が視界に入り、かすかな消毒液の匂いが漂っていた。一体ここは何処だろう。亜実は思った。起き上がろうと体を動かすと頭に鈍痛が走り目眩がした。右の額の辺りに手を持っていくとそこには何かがまかれていた。突然、昨夜の記憶が蘇った。亜実はマンションの近くの公園で暴漢に襲われた事を。その後の記憶は全く無かったが、自分が病院に運ばれ手当てを受けたのだという事をようやく悟った。現実に引き戻された亜実は部屋の壁に掛けられた時計に目をやった。午前8時20分だった。今日の10時に大事な会議の予定が入っていた。亜実は痛む頭をさすりながらベッドから抜け出し、病室の扉を開けて廊下に出た。突き飛ばされた時に膝も打ちつけたらしく、膝に出来た青い痣が歩くとずきずきと痛んだ。廊下の端に看護婦の詰所があった。中では3人の看護婦が忙しそうに働いていた。亜実は廊下側からカウンター越しに中のデスクで書類を整理していた年配の看護婦に声をかけた。
「あの、すみません」
亜実に気付くと看護婦は驚いた目をして立ちあがった。
「あら、あなた寝てなきゃ駄目じゃない。かなり頭を強くうっているみたいだから。ひどい脳震盪なの。だから、今日先生にみてもらわなきゃ」
看護婦は詰所の脇のドアを開けて廊下に出てきた。亜実の腕を脇から抱えるようにして掴むと、病室に戻るように促した。
「私、大事な仕事があるんです」
「そんなの無理よ。今日は大人しくしてなさい。分かった?」看護婦は子供を叱る母親のような口調でいった。看護婦の言葉が亜実の心に反響した。『分かった?』 これと似たような場面に遭遇していた。急に寒気がしたかと思うとあの時の恐怖が蘇ってきた。そうだ、あの男は私の頭を乱暴に振りながら『分かったか?』と言ったのだった。ナイフの刃で頬を撫でたまわしたのだ。亜実は思わず手で自分の頬を触ってみた。あの時の様子が走馬灯のように思い出され、あまりの恐怖に亜実は立っている事が出来ず、その場で倒れそうになった。看護婦はそんな亜実の腕をしっかりと掴み、何とか彼女を支えた。
「ほらごらんなさい。ちゃんと寝てなきゃ駄目よ」
亜実は看護婦に連れられて病室に戻ると、ベッドに横になった。看護婦に頼んで会社と鎌倉にある実家の母親に連絡をいれてもらう事にした。亜実は何もない白い天井を眺めながら、昨晩の暴漢が市田が差し向けた者であると確信したのであった。 |
|